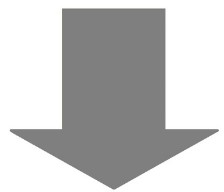お子様に吃音の症状が出ると「何かできることはないかな」「どのように接したらいい?」などと不安になる方がいるのではないでしょうか。
吃音のお子様を育てる際には、吃音についての基本的な知識を押さえて、話しやすい環境を整えることが大切だとされています。本コラムでは以下について説明します。
● 吃音の基本的知識
● ご家庭での配慮
● 家以外での環境の調整
● 専門家に相談する
● 吃音について話し合う
● 対応を考える際には本人の希望を確認する
お子様にとって話しやすい環境をつくり、症状に関する困りごとを軽減するためにお役立てください。

(言語聴覚士 大井純子)
吃音とは
吃音とはなめらかに話すのが難しい発話障害のことです。
保護者の育て方の影響で発症すると誤解されることがありますが、正しい情報ではありません。

くわしい原因については十分に解明されていない一方で、発症の原因の約7割は本人の体質などによるものだということはわかっています。
吃音の症状
吃音のことばの症状には、主に以下の3つあります。
| ことばの症状 | 症状の説明と例 |
|---|---|
| 音の繰り返し(連発) | 最初の音をくり返す 「ぼ、ぼ、ぼ、ぼく」 |
| 引き伸ばし(伸発) | 音を伸ばす 「ぼーーーく」 |
| 音のつまり(難発、ブロック) | ことばの出だしがなかなか出てこない 「………っぼく」 |
連発、伸発の症状から始まる方が多く、それを阻止しようとして力を入れることなどから、年齢を重ねるとブロックの症状が増える傾向にあります。
ブロックは声自体が出ないために、連発・伸発に比べて周りから気づかれにくいです。そのため「反抗してわざと返事をしない」「不勉強だからわからない」と誤解されることがあります。
症状についての詳細は「吃音症の症状」のコラムをご覧ください。
経過
吃音の経過についてはいくつかの研究結果があります。吃音は2歳~4歳頃に発症することが多いとされており、発症率は全体の5%程度です。
つまり20人のお子様がいたら、1人程度は発症するといえるのです。
吃音の症状自体に波があり、時期により出やすくなったり出にくくなったりを繰り返します。そのため、短期間での症状の変化について一喜一憂しすぎず、数ヶ月といった長いスパンで見守るのが大切です。
幼いころに発症した吃音のお子様のうち約74%は、とくになにもしなくても4年程度の間に自然に回復するといわれています(菊池(2012)p.12)。
症状の進展
自然回復しなかった場合には、吃音の症状とともに成長していきます。
吃音には「進展」という側面があり、下表の「第1層」から「第4層」の方向に向かって、症状や感情が変化することをさします。
吃音の進展段階
| 吃音症状 | 認知および感情 | 本人の悩み | 周りの心配度 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1層 | ・連発(繰り返し) ・伸発(引き伸ばし) |
・全ての場面で自由に話す ・吃音の自覚(-) ・まれに瞬間的なもがき |
小
? |
中 |
| 第2層 | ・難発(阻止:ブロック) ・随伴症状が加わる ・連発・伸発もある |
・自由に話す ・吃音の自覚(+) ・非常に困難な瞬間は、「話せない」など言うことがある |
大
? 小 |
|
| 第3層 | ・回避以外の症状あり ・緊張性にふるえ ・語の言い換え |
・発話前の予期不安(+) ・吃音を隠す工夫を始める ・吃音を嫌い、恥ずかしく思う ・恐怖(-) |
||
| 第4層 | ・回避が加わる ・一見、どもっていない ・連発・伸発は減少 |
・吃音に恐怖(+) ・話す場面を回避し、周りの人に誤解される ・1人で吃音の悩みを抱える |
- 随伴症状:ことばの症状に不随して表れる身体の症状
- 予期不安:話す前に失敗するのではないかと不安になること
(菊池(2012)p.13参照)
吃音が進展すると一見周囲からは症状が軽くなったように見えます。しかし実際は、苦手なことばを言い換えたり、話す場面を回避したりすることによって成り立っている可能性があり、吃音者の心情としては、話すことへの悩みが大きくなっていると考えられるのです。
吃音では、表面上のことばの症状だけでなく、症状に伴う認知・感情面についても見守り、本人が話す場面に苦痛や恐怖を感じやすくなる「進展」を防ぐことが大切だといわれています。
周囲から吃音についてからかわれたり笑われたりすると、症状の進展が生じやすいことがわかっています。吃音について周囲に理解を求めるのが大切だとされる理由です。
吃音のお子様を育てる際に考えるポイント
吃音のお子様を育てる際に考えるポイントについて説明します。

ご家庭で話しやすい配慮をする
吃音の症状を軽減するためには「できるだけなめらかに話す時間を増やすのが良い」とされています。そのため会話する際には、以下のような話しやすい環境を整えるように意識しましょう。
- 吃音が出ても最後までゆったり聞く
- 「落ち着いて」「ゆっくり」など、話し方のアドバイスをしない
- 吃音が出た際に言い直しを要求しない
- 周囲がゆっくり、たびたび間をとって話しかける
- 質問を減らす
- 家族全員で聴く・話す順番を守る
(参考:幼児吃音臨床ガイドライン 添付資料 4「お子さんがどもっている(きつおん吃音がある)と感じたら」)
話し方のアドバイスは、効果がないばかりかプレッシャーになるため避けましょう。アドバイスをせずに、周囲が見本となるゆっくりした話し方をすると、お子様も真似します。
たとえ吃音が出ていても、内容を先取りしたりさえぎったりせず、最後までゆったり聞くと話す意欲が高まるでしょう。
家以外の環境を整える
症状の進展でも説明した通り、吃音の進展を防ぐためには、家以外の環境を整えることも大切です。たとえば保育園や幼稚園、学校などがあります。
環境を整える具体的な内容としては、「話しやすい環境をつくること」、からかいや笑いといった「話すのが嫌になる環境を避けること」です。
担任の先生には事前に吃音について伝えておいて、以下のようなお願いをすると助けになってくれるでしょう。
- 吃音のからかいがあったらやめさせる
- 話すのに時間がかかっても最後までゆったり待つ
- 「落ち着いて」「ゆっくり」など話し方のアドバイスをしない
- 発表や音読などの対応を本人と相談する
お願いする内容については基本的にご本人の意思を尊重します。担任の先生へ吃音について知らせるときには、資料を渡すと理解してもらいやすいでしょう。
吃音に関する配布資料は、『吃音の合理的配慮「巻末資料PDF」』をご覧ください。
必要なときに専門家へ相談する
ことばのリハビリの世界では、吃音の症状で困ったり不安になったりしたら、言語発達の早い段階から専門家にサポートしてもらうのが望ましいと考えられています。
理由としては、幼いうちの方が訓練の効果が出やすいこと、ご家族が吃音について理解して正しい対応がしやすくなることがあげられます。
しかし実際は、自然治癒する割合が多い(約74%)、専門家が少ないなどのために、最初は経過観察となることが多いのが現状です。
専門家への相談が難しい場合には、先ほどお伝えした「ご家庭で話しやすい配慮をする」「家以外の環境を整える」について対応すると、話しやすい環境をつくることにつながります。
そのうえで以下を目安に、専門家への相談を視野に入れてもいいかもしれません。
● 4歳~5歳以上
● 症状が1年以上継続している
● 就学1年半前になっても吃音の症状が軽くならずに続く・悪化する
● 本人が症状で困ったり苦しんだりしている
(参考:幼児吃音臨床ガイドライン 添付資料 4「お子さんがどもっている(きつおん吃音がある)と感じたら」)
(参考:発達性吃音(どもり)の研究プロジェクト「A04/05-2 治療にとりかかる時期について」)
なかでもご本人が症状について困っている場合には、早めの相談がすすめられます。
吃音について避けずに話し合う
「吃音について意識させると症状の悪化につながる」として、本人と話さないように気をつかう方がいますが、吃音について話し合うこと自体には問題がなく、大切なことです。
海外の研究結果では、吃音のお子様は2歳時点で6割弱、4歳になると約7割で吃音の自覚があるとわかっています「(菊池(2012)p.49)」。いずれ自分の症状について疑問をもち、質問してくるでしょう。
吃音について自ら質問や相談をしてきた場合に、きちんと話し合わずにうやむやにすると、症状についての悩みを相談できる場がなくなります。
日頃から症状について話し合って、困ったときに「困った」といえる関係を築いておくことが大切です。
友だちから症状について質問される場面でも、ご家庭で話し合っておくと困らずに説明できるでしょう。
友だちへの説明例は以下を参考にしてください。
- 吃音はことばの障害であること
- わざとしているわけではなく、自然な話し方であること
- 真似したり笑ったりせずに最後まで聞いてほしいこと
(菊池(2014)p.18)
友だちに聞かれたら、隠したりうやむやにしたりするよりも、自分できちんと説明できるほうが、その後に協力してもらいやすいと考えられています。
吃音のお子様が困る場面では本人の希望も確認して支援を依頼する

吃音のお子様は、園での生活や学校生活、就職などに際して困る場面が想定されます。その時々でどのような対応策があるのかを押さえておくと、困った際の助けになるでしょう。
| 想定される困る場面 | 依頼する支援例 | |
|---|---|---|
| 全体を通して | クラスでのからかいや笑い | ● からかいは止めるように指導する ● 事前にクラスメートに症状について公表して配慮を依頼する |
| 園や小学校 | ● 音読 ● 日直 ● 自己紹介 ● 劇や発表会 ● 入学式や卒業式 ● かけ算九九 |
● 最後までゆっくり聞く ● 「ゆっくり」「おちついて」など言わない ● 吃音の調子が悪いときにはあてない ● ことばが出ないで困るときには、最初のことばだけ一緒に言う ● 誰かと一緒に言う(同時に言うと症状が出にくいため) ● 九九などは時間制限を緩和する |
| 中学校以降 | 入学試験 | 時間的な余裕を確保する |
| 学習発表 | ● 録音音声の使用 ● 読み原稿をパワーポイントなどで表示する |
|
| 英検 | 発話への配慮や筆談への変更 | |
| 就職試験 | 面接の練習 |
(菊池(2019)pp.38-111)
(参考:「Ⅱ. 分担研究報告 吃音症の実態把握と支援のための調査研究」)
吃音は「障害者差別解消法」の対象です。表のように、学校生活や就職において、症状が理由で不当な扱いを受けないように、求める権利があります。
ただし注意が必要なのは、お子様によって「求める支援が違う」点です。
授業中にしてほしい支援について、吃音のお子様にアンケートを行なった過去の結果では「他の子と区別しない」対応を希望するお子様が30%以上いました「(菊池(2012)p.63)」。また、クラスメートへの公表は嫌がるお子様も多くいます。
ご本人が望まない対応を周囲にお願いしてしまうと「本当は皆に知られたくなかった」「挑戦したかったのにできなかった」などと残念な気持ちにつながります。
求める支援についてはお子様とよく話し合うといいでしょう。
吃音症状に対して依頼する支援の詳細は「【親御様や先生向け】 吃音を持つお子様との関わり方」のコラムをご覧ください。
まとめ
吃音のお子様は、話しやすい場面を多く経験するのがいいとされています。周囲が吃音について理解したうえで、最後までゆったり聞いてくれる環境をつくれると、話しやすさの手助けになるでしょう。
会話時の配慮や環境を調整したうえでも症状が続く場合や、お子様が症状に悩む場合などには、専門家への相談を検討するのも1つの方法です。
地域の保健センターや都道府県の言語聴覚士協会、発達障害者支援センターなどに問い合わせると、相談先を教えてもらえるでしょう。
学校生活や社会生活での困りごとが生じた際には、お子様と話し合って学校などに依頼する支援を考えておくことをおすすめします。そのためにもお子様と症状について話し合っておくことが大切です。
参考文献
- 菊池良和『エビデンスに基づいた吃音支援』学苑社
- 菊池良和(2014)『備えあれば憂いなし 吃音のリスクマネジメント』学苑社
- 菊池良和『吃音の合理的配慮』学苑社
- Ⅱ.分担研究報告 吃音症の実態把握と支援のための調査研究
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202018006A-buntan2.pdf - 発達性吃音(どもり)の研究プロジェクト
http://kitsuon-kenkyu.umin.jp/guideline/index.html
「幼児吃音臨床ガイドライン2021」
「幼児吃音臨床ガイドライン添付資料4」
「治療にとりかかる時期について」
https://plaza.umin.ac.jp/kitsuon-kenkyu/qa/a04%e3%83%bba05/a04%E3%83%BBa05-2/index.html - 学苑社ホームページ 吃音の合理的配慮 巻末資料PDF
https://www.gakuensha.co.jp/news/n40614.html